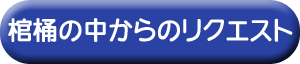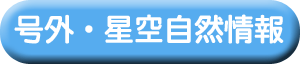BCL 時々の雑感
山梨県で国内中波を聞く
小笠原でBCL
スカイセンサー5500オタク
DE-1103 vs ICF-2001
SANYO RP8700インプレ
TOSHIBA RP 775Fインプレ
1975年版ベリカード
2023年版ベリカード
沖縄局の直接波を受信 ! 御前崎でBCL 2024
御前崎ペティ・リベンジ・IC-R75
2025.8.23 記
夏、土曜日の朝、御前崎海岸の駐車場はすでにサーファーの車でいっぱいだった。
予想していない状況にあせりを感じたが、とにかく周りの目などは気にしていられず、サーファーの車の間に駐車し、アンテナを上げた。
受信してみると、ガリガリ雑音がひどい。これは周りの車の影響かもしれないと思い、車を空いているスペースに移動した。
とにかく暑い。じっとしていても汗が出る状態で、高温による機器への心配もあった。
再びアンテナを上げ、受信するとガリガリ音はかわらず、自然環境からのものと判断し、狙いの沖縄中波局を探波した。
リグとアンテナは IC-R75+Δループ7。
・549kHz NHK第一・那覇局・10kW
・738kHz 琉球放送・10kW
・864kHz ラジオ沖縄・10kW
これらは混信あるものの、すべて受信でき、ところどころ内容も聞き取れた。(9時台)
今回も耳の良いDE-1103、ICF-2001と併用したが、今回はさすが!IC-R75に軍配が上がった。サイド混信のある琉球放送とNHK第一は、
確認の有無での大きな差が出た。
IC-R75の探波機能はこのような「過酷な状況」で発揮されるものと認識したわけだ。
特にイメージ波の有無は重要であることが体現できた。
もしも混信波がイメージであれば、その有無は明らか。
実際にICF-2001とIC-R75を738kHz 琉球放送で受信比較したが、ICF-2001には明らかにイメージ波のサイド混信があり、IC-R75にはなかったのだ。
ICF-2001の経年劣化?と、IC-R75のトリプルスーパーの差と言いえよう。
この3局で一番強く入感するのが、864kHz ラジオ沖縄で、あとの2局は弱く、 通常は「聞こえない」と判断される状態。サイド混信の中から機能を使い、音声を浮き上がらせてやっと確認ができるような感じだ。
10時台になると全体的に電波が弱くなってきた。動画記録がままならなくなり、熱波から避けるためにも一度涼しい図書館へと避難した。
午後、電波の状況が良くなることを期待して、偶然見つけた、浜岡原発の隣にある風力発電のたもとの海岸で再びアンテナを上げた。
風力発電機から出る雑音の有無が気になったが、実際はなかった。それに周りに他者がいない場所だけにホッする。
この場所では14時頃〜16時頃までいたが、受信結果として電波の状況はあまり変わらなかった。
後半にかけてやや状況が良くなる傾向だった。
3局とも受信できたが、言葉の聞き取りまでは出来ない状態だった。
ともあれ、かねてから失敗続きであった御前崎リベンジペディ。一度気が済んで、あとは電波の季節差を観察に行くことかな。
なんせ、初めての遠征では、冬場、DE-1103+60角バッシプループで琉球放送を内容まで確認している。
だから、手持ち最強のIC-R75+Δループ7で受信報告書を書ければと思っているわけだ。
直接波の伝搬変動の要因
2025.8.22 記
直接波は電離層反射波のような「変動はない」と思っていたが、そうではないことを知った。
ペティで、例えば、かすかに聞こえる九州のRKB・1278kHzをの直接波を昼間受信していると、
聞こえなくなったり、聞こえたり、一定しない。
調べてみると、
電子情報通信学会『知識の森』で、
直接波は気象粒子(雨。雪など)による減衰が作用があることを知った。
だから、かすかな直接波を狙う場合、対象局との間に低気圧が「あるか・ないかで」、聞こえ方が違ってくるかもしれないので、
今後は季節や気象もリンクさせていこうと思う。
感度の良いラジオとは?
2025.8.21 記
一般に「感度の良いラジオ」というものは「弱い電波を受信できるラジオ」という意味でとらえられている。
しかし、その「感度」には内訳があり、ラジオ本体(機器)の「感度」レベルとアンテナの「利得」レベルの合算としてある。
感度(一般)=感度(機器)+利得(アンテナ)というややこしい言葉の理屈になっている。
例えばアンテナ一体型のラジオでは、合算としての「感度(一般)」を言うが
アンテナ分離の通信機型のラジオ(受信機)では、アンテナ次第で感度(一般)はどうにでもなるのだから、一体型のラジオとは比較ができない。
このように「感度」という言葉がダブルスタンダードになっていて、わかりづらいので、一般に使われている「感度」という言葉を「総感度」に変えれば良いのかと思う。ようするに、
総感度=感度(機器)+利得(アンテナ) で、
「感度」と言えば機器の持つ感度性能をさし、「利得」と言えばアンテナの性能をさす、とすればよいわけである。
機器のもつ「感度」は、スーパーヘテロダインなどによる増幅の度合いで、μdBなどの数値で表される。
よく「ダブルスーパ−ヘテロダインだから感度が良い」と言われる。しかし、それは一理あるものの、「だから、このラジオにしか受信できない凄いもの」にはならない。中波に限って言えば、ダブルスーパーは実用過剰とされる。ダブルスーパーは短波帯などに出やすいイメージ波の抑制が大きな目的で、入力波の増幅は第一の目的としていない。
だから、中波ラジオで「感度(総感度)が高いラジオ」として有名な「SONY ICF-EX5」もシングルースーパーだ。
(機器の感度数値は良いものであることに越したことがない)
アンテナの利得性能はdBという数値で表される。
ふつうのラジオには機器本体に「中波用内臓バーアンテナ」と「短波、超短波用のホイップアンテナ」が付けられている。
通信機型ラジオ(受信機)はアンテナは外付けとなっていて、別に用意する必要がある。
だから「感度(総感度)の良いラジオ」というのは「アンテナ」で決まる部分が大きい。
SONY ICF-EX5は内蔵バーアンテナが長いことがアドバンテージとなっている。
手のひらサイズのラジオは筐体的にバーアンテナの長さが短いから、ふつう中波の感度(総感度)は低いことが見た目でもわかるだろう。
(ただし中波もホイップアンテナが適用されていたなら別)
このようにアンテナ一体型のラジオは、内臓バーアンテナ・付属ホイップアンテナの大きさが筐体によって制限されるので、その総感度は筐体の大きさに比例していると考えれば良いだろう。
巷では耳障りのいい「感度の良いラジオ」というフレーズが独り歩きしているが、その評価基準は一定でないので注意が必要だ。
中波(直接波)ペディで受信機とアンテナ比較
2025.8.15 記
受信機は
・IC-R75(FL-257・UT-106装備)
・DE1103(初期型・外部アンテナ入力、裏ワザ設定・プリアンプON・フィルターON)
アンテナは
BCLerに有名なものなので詳細は割愛。簡単に説明すると、
・Δループ7は1m角6回巻(三角)アクティブ・同調式
・パッシプ60角は60cm四角ハッシブ・同調式。
★Δループ7の場合
はじめから強力な信号が入るので、受信機側のプリアンプ性能の差は出ない。
・IC-R75は各機能の「効果」があるけれど、オーディオ性能が悪く、フィルター幅を狭めると音がこもってしまい、せっかく弱い電波をキャッチしても「聞き取り了解度」が良くなく残念。ここが弱点。フィルターはワイドを使える時であれば、DE1103との差は縮まる。
・DE1103はノイズ/音声のコントラストが良く、IC-R75より「聞き取り了解度」が良いです。(驚き)
★パッシプ60角の場合
・IC-R75はプリアンプ効能が大きく・プリアンプON・2の場合、Δループ7の「8割」程度の入感。
・DE1103はプリアンプONでも、IC-R75に比べると効果が低くΔループ7の「3割」程度の入感。
★聞き取り了解度 ・IC-R75はフイルターONの場合、音がこもって聞き取りが厳しくなる。 ・DE1103はフイルターONでも音のこもりはあるものの、聞き取りしやすい。
★ノイズ除去
・IC-R75はフィルターとノッチ・ノイズブランカによる除去機能がある。
ただし、ノッチ・ノイズブランカの有効性は限定的なので万能ではないが、ハマれば効果絶大。
ノッチ機能は、特にUSB・LSB受信でサイドからのピー音をばっさり除去できる時がある。
・DE1103はデフォルトで調整されている。
★選択度
・IC-R75はフイルター・TWIN BIT機能により可変できる。
サイド混信のブロックはAM受信でもDE1103より狭めることができる。
・DE1103はフイルターは2段階切り替えだが、しっかりとした効果がある。
★混変調
・IC-R75はさすが、混変調の耐性は高い。
・DE1103は短波帯や長波帯で混変調を何度か確認、混変調の耐性は実用性には問題ない範囲。
★考察
・昼間の中波・直接波受信で、しかもとても弱い電波の場合、「アンテナがΔループ7の場合」は、聞き取り了解度が良いDE1103に軍配があがる場合がある。この結果は多機能をもつIC-R75にとっては「屈辱」であるが、聞き取りオーディオの機能を「軽視」したため、せっかくの機能が「だいなし」になっている。
弱い電波の場合、IC-R75の「LSB・USB受信技」は、さらに入力が弱くなるので、かすれ音だけで、言葉の認識はできなくなることが多い。両帯のAM受信でやっと言葉の聞き取りができる弱い電波では、絶大な優位性はない。
ただし、夜間の短波帯ではAM波なのに、なぜか片側帯だけ届いている電場の場合には機能を発揮する。
例えはDE1103では雑音だけなのに、IC-R75のLSBで聞くとちゃんと音声が聞こえる場合がある。
また、IC-R75のオーディオ欠点を補うために、出力音声に対しの調整装置を外付けする場合がある。しかし、これは室内電源があるからできる技で、ペディに付属させることはハードルが高い。
・アンテナが「パッシプ60角」の場合はあきらかにIC-R75に軍配があがる。
これは、プリアンプ機能の差によるもの。
それならなぜ、Δループ7ではプリアンプの差が大きく出ないのかというと、すでにアンテナ側からの入力が強く、最大値に近いため、そこから受信機側のプリアンプを入れても飽和してしまうので、受信機側で抑制効果が働くためと思われる。
★総評
昼間の中波・直接波局受信においては、Δループ7+DE1103が良い場面がであった。
結局、IC-R75の高い選択度機能があっても、「弱い電波の聞き取り了解度」が重要ということだ。
サッカーで言えば、ゴール前までの玉運びはIC-R75が凝っているが、最後のシュートを決める精度はDE1103が
優秀である。ということだろう。
しかし、多機能をもつIC-R75は「探波を極める」という意味では、言うに及ばずレベルが違った。
グレーゾーンパス時間帯に聞こえるブラジル局
2025.8.11 記
グレーゾーンパス時間帯(18:00〜19:00)にブラジル局を受信してみた。
比較的強く聞こえるのは
6080kHz・R・マルンビー・10kW で、
弱く聞こえるのは
5940kHzと11750kHz(中国CNRの裏で)のパラの R・Voz・ミッショナリア・10kW
6180kHzと11780kHz(弱く)のパラを確認の RN・ダ・アマゾニア・10kW
ブラジル局以外では、5020kHzのソロモンBCが良好に入感しています。
受信機 IC-R75
アンテナ 「短波用アクティブ・ループ・アンテナの製作」 ΔLOOP10
夏はハイバンドが聞こえる!
短波放送局でめぐる 海外電波旅行
2025.7.29 記
夏になると短波帯でも高い周波数帯が聞こえて面白い。
22時台に短波を受信していると、思わぬ国からの電波が受信できた。
まず、21.565kHz・BBC・マダガスカル中継局(英語)・250kW が良好だ。
以下、列記すると
15460kHz・オーストラリア・クマナラ・10kW
15475kHz・ふるさとの風(韓国語)・ウズベキスタン・タシュケント・10kW
13610kHz・ルーマニア・30kW(弱く入感)
5985kHz・ミャンマーラジオ(ビルマ語)・25kW
4755kHz・インドネシア(インドネシア語)・10kW
電波の海外旅行は、スマホ片手に Short Wave dot Info を見ながら、海外電波旅行が楽しめる。
受信機 IC-R75
アンテナ 「短波用アクティブ・ループ・アンテナの製作」 ΔLOOP10
楽しい野外BCL(ペディション)
2025.7.28 記
WIKIベディアによれば、「ペディションは"DX"と"expedition"(遠征)を組み合わせた言葉」。
家で受信機に耳を傾けるのもいいけど、ノイズの少ない野外での受信はおもしろい。
御前崎ペディを期に近場の山岳域でのペティに気づいたのだ!
狙いは近畿以西局の直接波で、どの局が聞こえるか?というもの。
早速、散歩がてら、山梨県と長野県の県境にある観音平(標高約1500m)に行ってきた。
ここは八ケ岳・編笠岳、権現岳への登山口で、夏の休日はとてもにぎわう。
山梨県は四方を山に囲まれているので盆地ならば直接波は遮断されるけど、逆に山岳に沿った高台も多い。観音平では北に八ケ岳を背負うけど、「東〜南〜西」が見渡せる場所になつている。といっても南は南アルプスが連なっているが・・。
受信装備は念願のIC-R75・Δループ7だ。IC-R75の電源確保も解決して、なんとか「さまに」なってきた。IC-R75の電圧は13.8Vで車のバッテリーのシガー直では、電圧不足と思いきや、大丈夫でした。
DC先端プラグも変換ブラグが見つかって、それもバッチリ。
今はやりのポータプル電源(IWASHN GP50)も考えたけど、3万円のお値段は他の受信機が買えちゃう値段で・・。Δループ7の電源もシガー12Vで動作するので問題ない。
受信結果はすばらしく、以下に列記。
徳島県・四国放送・1269KHz・5kW・中
福岡県・RKBラジオ・1278kHz・50kW・弱
福岡のRKBラジオが受信できたのは、出力が強いことと、観音平が瀬戸内〜大阪平野〜京都盆地を通過する障害物の少ない地形にあるからだろう。しかし、日時によっては受信できないこともあり、直接波も変動があることがわかる。
広島県・中国放送・1350kHz・20kW・かすか
富山県・北日本放送・738kHz・5kW・中
石川県・北陸放送・1107kHz・5kW・中
福岡県・RKBラジオ・1278kHz・50kW・弱
1975年版ベリカード
2025・静岡県御前崎で3度目のBCL
2025.6.26 記
先日、静岡県御前崎に再びラジオ沖縄の直接波を聞きに行ってきた。
すでに、「聞こえる」ことはこのコラムで報告しているが、今回はIC-R75とΔループ7を装備して、しっかり聞こうという算段だ。
結果はもちろん聞こえ、受信報告書は書けたが、IC-R75が使えず不完全燃焼となった。
その原因はIC-R75の電源の問題だ。IC-R75はそもそも移動用にはできていなく、シガープラグ対応の純正パーツは国内向けにはないようで・・。しかもDCプラグのサイズが少し違ったもので、自作しようとも、変換プラグやプラグ単体の部品が見つからず、仕方なしにACインバーター経由で給電した。
もちろん、本体の動作は問題ないのだが、このインバーターからノイズが出て、思うような受信が出来なかったのだ。
だから今回も電池駆動のDE-1103での受信となった。
アンテナはΔループ7の中波用で、エレメントは巻線数が多いタイプ。給電はシガー電源でOK。
さすがに前回の非電源ループアンテナよりよく聞こえ。報告書がなんとか書ける状態に。
ただ、DE-1103ではノイズが多く、やはりノイズ除去装備があり、USB・LSB受信ができるIC-R75で聞いてみたかった。
動画を撮影して、その状況をUPしようと思ったが、それも失敗!。マイクのノイズキャンセラーが利きすぎて音が×に。
受信報告書用に別録りした「受信声」もありUPしたいのですが、面倒で・・。
ベリカードの返信があったらUPします。
その後、IC-R75のDC変換プラグが見つかったので、再度、御前崎に行こうと思っている次第です。
次回は、うまく受信できればいいな!
夜、864KHz・FBC福井放送が聞こえている。
2025.6.13 記
なんとビックリ、鬼門難局の福井放送が21:00頃の夜に入感しています。
季節的な現象なのか?、もちろん同波のKBS韓国が混信しますが強弱があり、その間を縫う入感です。
近隣のSBS松本局の混信は弱く、ラジオ沖縄もほぼ届いていません。
電波が強い時は、混信やノイズがほぼ入らない聞こえ方です。
夜帯はキー局ネットの統一番組で「福井」の確認は正時前後のCMに限定されますが、その中で
22:57分頃の天気予報では地域名が出ますのでおすすめです。
1975年のベリカードをUPしました
2025.5.25 記
最近、実家から1975年に集めたベリカードが発掘されたので、参考にUPしました。
1975年版ベリカード
BCLの動画の感想
2024.5.21 記
「まっとさんのラヂオ部屋」はほとんど見ました! 話題豊富、威張らず、やさしい人柄に癒されます。
その中でいろいろなアンテナがレビューされていて、おもしろいです。
私のBCL復活は影山さんのΔループの時代でしたが、今ではそれも過去の出来事になってしまっているようでさみしいです。
現在のアンテナ事情ですが、シールドループアンテナを良く耳にします。そしてApexRadio 303WA-2は不朽の名作ですね。
その中でBCLerの間で評価の高いTECSUN AN-200ですが、書き込みレビューには厳しい声が多く、気になりました。
この評価はおそらくBCLerではなく一般の人と思います。
アンテナを自作している人には、そのコスパに驚かされるのですが、一般の人は、その体験がないから、「驚くほど効果のあるもの」と思っているのでしょうね。
これほど価値基準が違うのも珍しいです。
御前崎で聞く沖縄局の情報
2024.5.21 記
1月31日に行った御前崎からのBCLで、ラジオ沖縄(864kHz)が同波に東海ラジオ豊橋局があったため、聞こえませんでしたが、東海ラジオ豊橋局が、2024年8月1日〜2025年1月31日まで停波するので、停波期間に受信できるかも知れません。
静岡県御前崎でBCL・昼間、738kHz 琉球放送の直接波をキャッチ
2024.1.31 記
前から気になっていた、昼間、沖縄局の直接波が本州から聞こえるか?という課題の調査をしてきました。
静岡県御前崎から沖縄までは約1348km、障害物のない海上。直接波が聞こえそうな場所です。
実際は簡単には聞こえなかったですが、ループアンテナで10:00頃、738kHzの琉球放送の「沖縄情報」を確認し、受信成功です。
リグはDE1103とICF2001。ループアンテナは自作、60cm角、12回巻、エアバリコン製。
まず受信機単体で。DE1103ではビート音のみ確認し、ループアンテナで内容が確認できました。
ICF2001は雑音、混信音の混沌の中から音声がわずかに確認できる程度。ループアンテナは接続線を忘れ×。
ループの中に本体を入れても効果がなかった。なぜ?
DE1103+ループアンテナでは、アンテナ方向の調整が微妙でした。また、12:00頃は電波が弱くなり、聞き取りが難しくなりました。
琉球放送の738kHzはまず729kHzのNHK第一名古屋からサイド混信を受けます。
そしてループアンテナを北に向けるとなんと富山の北日本放送が聞き取りできる強さで入感します。
琉球放送はアンテナを北日本放送のヌル方向の西南西方向に向けると、弱く聞こえてきます。
しかし、直接波でも時間帯で強弱があるのか?安定しませんでした。
864kHzのラジオ沖縄は東海ラジオ(愛知県豊橋)と同波で、その裏で弱く聞こえ、内容は確認できませんでした。
おそらく、これらの混信局がなければ、なんとか聞き取りもできる状態です。
要するに、沖縄局の昼間の直接波(御前崎−那覇 約1348km)は「簡単には聞こえないけれど、受信できた」ということです。
御前崎からの受信の特筆は、936kHzの宮崎放送(御前崎-宮崎市・約700km)と1557kHzの和歌山放送御坊局0.1kWが良好でした。
1107kHzの南日本放送は、鹿児島市が内陸にあるので、ループアンテナで何とか内容が確認できる程度で、900kHzの高知放送も地形の影に入りとても弱いです。
関東方面は1485kHzのラジオ日本(神奈川県小田原局)はもちろんのと、1530kHの栃木放送、1197kHzの茨城放送もわりあい良く入りました。
ちょっと驚きは、内陸の山梨放送765kHzはかなり強く入り、ループアンテナで北日本放送が入ったのは驚きです。
おそらく地形的に御前崎は山陵からの距離があるから(遠い)と思われます。
カーラジオでのログは次の通り
DE1103やICF2001では もっと良く聞こえます。
2段目のS値は
0.5、かすかに人の声を確認
1、 耳を凝らせば内容の一部確認
2、 内容確認できる
3、 普通に番組が楽しめる
4、 電波が強いが時々雑音混ざる
5、 雑音混ざらず電波が強い
540kHz 2 NHK第一 (宮崎または沖縄石垣)
558kHz 5 ラジオ関西 (兵庫)
576kHz 5 NHK第一 (浜松)
585kHz 3 NHK第一 (京都・舞鶴ほか)
594kHz 5 NHK第一 (東京)
603kHz 3 NHK第一 (岡山)
612kHz 1 NHK第一 (福岡)
621kHz 2 NHK第一 (宮崎延岡または長野飯田または京都)
639kHz 5 NHK第二 (静岡)
648kHz 0.5 NHK第一 (富山)
666kHz 5 NHK第一 (大阪)
711kHz 韓国KBS1
720kHz 2 CBCラジオ(三重熊野) 0.1kW
729kHz 5 NHK第一 (名古屋)
747kHz 1 NHK第二 (北海道・札幌福岡)
765kHz 4 山梨放送 (山梨甲府)
774kHz 3 NHK第二 (秋田)
801kHz 3 CBCラジオ (三重尾張) 0.1kW
810kHz 5 AFN(東京)
828kHz 5 NHK第二 (大阪)
846kHz 0.5 NHK第一 (愛媛または熊本)
864kHz 4 東海ラジオ (愛知豊橋) 0.1kW
882kHz 5 NHK第一 (静岡)
900kHz 0.5 高知放送 (高知)
909kHz 5 NHK第二 (名古屋)
927kHz 4 NHK第一 (山梨甲府または岡山津山)
936kHz 2 宮崎放送 (宮崎)
945kHz 2 NHK第一 (滋賀彦根または徳島)
954kHz 5 TBSラジオ (東京)
990kHz 0.5 NHK第一 (高知)
1008kHz 5 ABCラジオ (大阪)
1026kHz 4 NHK第一 (静岡御殿場または和歌山)
1035kHz 0.5 NHK第二 (愛媛または高知)
1053kHz 5 CBCラジオ (名古屋)
1062kHz 4 静岡放送 (静岡掛川)
1098kHz 1 ラジオ福島または信越放送
1134kHz 4 文化放送 (東京)
1143kHz 3 KBS京都 (京都)
1161kHz 4 NHK第一 (愛知豊橋) 0.1kW
1179kHz 0.5 NHK第一 (高知)
1197kHz 1 茨城放送 (水戸)
1215kHz 1 KBS京都 (滋賀彦根)
1242kHz 5 ニッポン放送 (東京)
1269kHz 3 四国放送 (徳島県牟岐?)
1314kHz 4 ラジオ大阪 (大阪)
1332kHz 3 東海ラジオ (名古屋)
1350kHz 0.5 中国放送 (広島)
1359kHz 4 NHK第二 (愛知豊橋)
1368kHz 1 ?
1386kHz 2 NHK第二 (岡山)
1404kHz 5 静岡放送 (静岡)
1422kHz 4 ラジオ日本 (神奈川)
1431kHz 1 岐阜放送または和歌山放送
1458kHz 0.5 茨城放送 (茨城土浦)
1476kHz 0.5 NHK第二 (長野飯田?)
1485kHz 3 ラジオ日本 (神奈川小田原)
1521kHz 5 NHK第二 (静岡浜松)
1530kHz 1 栃木放送 (宇都宮)
1539kHz 2 NHK第二 (三重尾張)
1557kHz 3 和歌山放送 (和歌山新宮) 0.1kW
1584kHz 2 NHK第一 (徳島県牟岐または高知土佐清水または山梨県富士吉田)
1593kHz 1 NHK第二 (新潟)
1602kHz 2 NHK第二 (山梨甲府)
最後にDE1103とICF2001は単体でどちらがいいというと、
感度はブログ通り、ICF-2001が目に見えて良いですね。
2023年のベリカード集め 2
2024.1.3 記
地震や事故で幕開けした新年。緊張した正月となっています。
「能登半島でのBCL」について書いたばかりですので、なんともです・・。
さて、前年末15年ぶりとなるベリカードの状況を確認するために、集中して報告書を書きました。
今回はリグとアンテナをDE-1103・Δループ10→ IC-R75・Δループ10に変更しましたが、それらのまとめを他ページにUPします。
2023年のベリカード集め 1
2023.12.28 記
2009年以来、2023年に改めてベリカードを集め、UPしようと受信報告を出した。
この15年の間にベリカードの廃止局があり、びっくりしてる。
カード自体の経費は僅かな状況下、確認と返送に対する業務負担の軽減と合理化、そして受信報告件数の低下がそうさせていると思われる。
新潟県糸魚川市・道の駅・ピアパーク親不知でBCL
2023.12.16 記
機会があったので、日本海側の海岸で、カーラジオによるプチBCLをしてみた。
カーラジオで、西は韓国(約800km)、北は山形県、秋田県、北海道(札幌まで約750km)の局が聞こえ、びっくりです。
受信は昼間11時。直接波の受信。以下は受信の強さ。SINPOのS値のみ。「かすか」は0.5とした。
混信がないのでS=2であれは十分内容がわかる状況です。
先に書いたように、日本は弓型の島で日本海側では沿岸の都市からの電波は海の上を伝い受信できます。
今回の糸魚川は西に能登半島があるため遮られ、西日本の局はほぼ聞こえませんでしたが、
おそらく石川県能登半島の先端では昼間、北海道と九州の局が地元局と同じ感覚で聞こえていると思われます。
この考えで行けば伊豆半島や御前崎、房総半島突端などからは昼間、沖縄の局の直接波が聞こえる可能性大です。
沖縄局の難関ベリカードのGET方法として有力です。
参考HP「AMラジオ局周波数一覧表」
540kHz NHK第一(石川県七尾) 5
558kHz ラジオ関西(兵庫) 2
567kHz NHK第一(北海道札幌) 2
594kHz NHK第一(東京) 2
639kHz STVラジオ(北海道函館) 2
648kHz NHK第一(富山県富山) 4
657kHz 韓国KBS
675kHz NHK第一(北海道函館) 1
693kHz NHK第二(東京) 2
738kHz 北日本放送(富山県富山) 4
747kHz NHK第二(北海道札幌) 2
774kHz NHK第二(秋田県秋田) 5
792kHz NHK第一(新潟県高田) 2
819kHz NHK第一(長野県長野) 1
837kHz NHK第一(新潟県新潟) 5
855kHz 韓国または北朝鮮 1
864kHz 韓国KBS 2
882kHz STVラジオ(北海道江差) 2
900kHz HBCラジオ(北海道函館) 2
918kHz 山形放送(山形県・酒田) 4
936kHz 秋田放送(秋田県・秋田) 4
981kHz NHK第一(新潟県柏崎) 1
999kHz NHK第一(新潟県糸魚川) 5
1026kHz NHK第一(?) 1
1035kHz NHK第二(富山県富山) 2
1062kHz 新潟放送(新潟県柏崎) 4
1089kHz 中国 1
1107kHz 北陸放送(石川県七尾) 5
1116kHz 新潟放送(新潟県新潟) 5
1161kHz NHK第一(北海道松前) 1
1206kHz 中国 1
1224kHz NHK第一(石川県金沢) 1
1287kHz HBCラジオ(北海道札幌) 5
1296kHz NHK第一(島根県松江) 0.5
1332kHz ? 0.5
1341kHz NHK第一(?) 0.5
1359kHz NHK第二(富山県富山) 2
1368kHz NHK第一(山形県鶴岡) 2
1386kHz NHK第二(石川県金沢) 1
1440kHz STVラジオ(北海道札幌) 1
1467kHz NHK第二(石川県七尾) 5
1503kHz NHK第一(秋田県秋田) 5
1521kHz NHK第二(?) 0.5
1530kHz 新潟放送(新潟県糸魚川) 5
1557kHz 秋田放送(秋田県本荘) 1
1584kHz NHK第一(石川県輪島) 2
1593kHz NHK第二(新潟県新潟) 5
ラジオ佐賀の受信は今がチャンス!
2023.12.11 記
混信周波数にあるラジオ佐賀(1458kHz)は受信難関局だったのですが、今が受信のチャンスです。
月曜未明の各局休止により、0:18からはほぼ独占で聞こえます。
0時に茨城放送が終了。0時5分に福島放送が終了。0時17分にRCC中国放送が終了します。
残る山口放送は、かすかな電波でほとんどわからず、東海放送は聞こえません。
日本海側、海辺での受信はすごそう!
2023.11.23 記
そう言えば、富山県宮崎海岸にひすい拾いのキャンプに行った時、昼間BCLをしてみたところ、なんと、山形放送、秋田放送の直接波が良好に受信できたことを思いだした。
日本は弓なりの島なので日本海側は内側向きでなので、遠い秋田、山形の直接波が届いているのだろうと思った。
それなら、能登半島の突端でBCLしたら、もっとおもしろいことになりそうだと・・
受信機 DEGEN DE-1103
アンテナ 内臓アンテナ
大出力局の地上直接波の受信
2023.11.23 記
中波の電波は昼間、電離層に反射しないので、昼間聞こえる電波はふつう「直接波」「回折波」と考える。
電波の出力が弱いと山地などの障害物に遮られ減衰するのだが、強引に強力な力で障害物を回折させて到達させることもできる。
NHKの基幹局は第一が100kW以上、第二は、なんと500KWというとてつもないパワーで送信している。
第二(教育)がなぜここまで強力かというと、山間、離島に住む国民に対して「教育が等しく公平に行われること」の使命があるからだろう。「いつ何時も聞こえない場所を作ってはならない」わけだ。
さて、大出力局の地上直接波がどこから届いているが調べてみた。するとなんと北海道・九州からも弱いながらも山梨県へ届いているのだ。
・567kHz NHK第一 札幌 100kW 聞こえない ピート音のみ
・594kHz NHK第一 東京 300kW とても良く聞こえるS=5
・612kHz NHK第一 福岡 100kW まあまあ聞こえる S=2
・666kHz NHK第一 大阪 100kW ふつうに聞こえる S=3
・693kHz NHK第二 東京 500kW とても良く聞こえるS=5
・729kHz NHK第一 愛知 50kW 良く聞こえる S=4
・747kHz NHK第二 札幌 100kW かすかに聞こえる S=1
・774kHz NHK第二 秋田 500kW まあまあ聞こえる S=2
・828kHz NHK第二 大阪 300kW かすかに聞こえる S=1
・873kHz NHK第二 熊本 500kW まったく聞こえない
という結果だった。大阪と熊本の第二500kW局が聞こえない理由として、おそらく送信指向性の問題かもしれない。
ただしこの直接波も、その日によって差異があるようで、「612kHz NHK第一 福岡 100kW」はN=1〜N=2の範囲にあるようだ。
受信機 IC-R75
アンテナ 「短波用アクティブ・ループ・アンテナの製作」 ΔLOOP10
「民放AMラジオ44局・2028年秋までにFM化」の足音
2023.11.22 記
茨城放送が「IBS茨城放送」の愛称から「LukyFM 茨城放送」の愛称となっていた。
AM波の受信報告書の宛名が「LukyFM 茨城放送」で、ちょっと違和感。
企業戦略としては、関東圏の局の生き残り方として、いち早くFM放送局としての知名度を上げることは理にかなっていると思います。
だけと少しさみしい。
さらに茨城放送は
「当社は総務省の「AM局の運用休止に係る特例措置」が適用され、2024年2月1日から7月31日までの6か月間、AM土浦・県西中継局1458kHzの電波を止め、その影響を調べることになりました。今回の特例措置は、AM放送からFM放送への変更を検討するに当たり、リスナーのみなさまなどへの影響を最小限にする観点から設けられたものです。みなさまにご理解を深めていただけるようお願い申し上げます」とのリリース。
あと5年。「民放AMラジオ44局・2028年秋までにFM化」の足音が聞こえてきました。
追伸
ということは、1458kHzのNBC佐賀放送の受信確率が上がるということですね。
1233kHz 長崎放送の受信状況
2023.11.22 記
1233kHz 長崎放送の受信にチャレンジしたところ、なんと、同波にNHK第一の新局が2017年に開局されていてびっくりした。AM局が廃止される流れの中、NHKはどうしたことか?
この新局、兵庫県の「新温泉・中継局・出力 500W」
長崎放送を聞く場合、関東では同方向のこの局が混信して、しかも年中無休の24時間営業。
せっかく日曜深夜の各局休止時間を狙っても水の泡となっていました。
算段(山梨県からの受信)では、周波数の青森放送はループアンテナでカット。同方向の和歌山放送は24時の終了を待ち、長崎放送だけの時間を期待しますが・・。
実際、長崎放送は終始、NHKの裏で聞こえていて、内容の確認はほぼ難しく、時より強くなる声を確認する程度でした。
受信機 IC-R75
アンテナ 「短波用アクティブ・ループ・アンテナの製作」 ΔLOOP10
動画「まっとさんのラヂオ部屋」に癒される
2023.1.6 記
年明け早々コロナで寝込むことになった。
つらいです。38度台の熱と喉、頭の痛みが3日続き、とにかく解熱剤で症状を緩和させて72時間寝っきりです。
枕元でいやしてくれたのがスマホでした。
BCLを検索すると、まっとさんのラヂオ部屋を見つけ、耳元で聞いているだけですが楽しく過ごせました。
ありがとうございました。
ハードオフ
2022.8.15 記
ハードオフに行ったら、ガラスケースの中にICF5500、ICF5500A、TRYX2000が陳列されていて驚いた。
昭和のBCL機も人気になっているということを感じた。
それにしてもヤフオク市場は活況が続いていて、値が下がりませんね。
DE1103
2022.8.15 記
以前、旅行に持って行ったDE1103が、帰ってから見るとチューニングダイヤルが外れてなくなっていた。
ショックでしたね。まあ、実際にはテンキー操作ができるので聞くのには問題ないけど、気持的には「歯抜けのなんやら」で、静かに見えない所に安置となりました。
そこで、ダイヤルを求めヤフオクなどでジャンク品を探すも×、
ダメもとで購入先に連絡をとった所、パーツのみの購入に応えてくました。
これこそ「有難う」です。
それ以後、無事に神棚に並べられ、七福神の一つとなっています。
不良品上等の中国製品の中、感謝感激です。
通信機型受信機・アルインコDX-R8が生産中止となっていた
2021.9.26 記
通信機型受信機・アルインコDX-R8が昨年2020年で生産中止となっていてびっくりした。
今後はプロ用以外は中古を探すか、通信機型ではないが、中国製のラジオを買うかの選択になっている。
昭和BCLラジオのオークション状況は活況が続いている。ICF-5900、 RF-2200はあいかわらずの高値推移。
RP-8700、RF-1150、RP775は安定。ICF-5800はテレビで紹介されたことの影響か?高値で推移している。
民放AMラジオ44局が2028年秋までにFM化へ。在京3局はAM停波も目指す
2021.8.10 記
とうとう国内AM局が停波。BCLファンにとどめを刺す一撃。さらに、つまらない世の中になっていきますね。
今、昭和BCLラジオ市場は活況で高値で推移しているけど、これ以上「聞こえる」放送局が無くなれば、その価値は一変するかもしれない。
実際に購入しても、受信する放送局がなければ、昭和のBCLラジオが「ただの昭和遺産としての外見」だけの存在になってしまうので、中身については「壊れていても良い」から価格は下落するかもしれない。
「完動品」の意味は薄くなる一方ですね。
ただ、BCL最後の打ち明げ花火として、徐々に停波するから、今まで混信していた局がとりのぞかれ、聞こえずらかった局が聞こえるかもしれないのと、放送業界さんもAM放送文化の幕を落とすにあたって、特別ベリカードの発行(ファーストベリカードのリバイバルデザイン)を業界全体でやってくれると嬉しいですね。
このくらいの「粋」があってもいいと思うのですが。
2021.9.26 追記
国内のAM局が終了した後、残存の海外AM局が楽しめるかもしれないと、ふっと思った。
新たなBCL領域が広がるかもしれない。
グレーゾーン・パスを狙ったブラジル局
2020.11.17 記
グレーゾーン・パスを狙って17:00〜ブラジル局が聞こえるか、チャレンジしたところ、「らしき局」を2局確認しました。
5939.50kHz R.Voz Missionaria 10kW LSBで受信
6134.82kHz R.Aparecida 25kW LSBで受信
受信機 IC-R75
アンテナ 「短波用アクティブ・ループ・アンテナの製作」 ΔLOOP10
ベリカードに対する民放局の浅い態度
2020.10.3 記
中波で民放局を聞いていると、時々「昭和レトロ」の話の中でBCLラジオやベリカードの話になる。
若い局アナは、ベリカードについて、へらへらと笑いながら、「へーっそんなのがあるんですかぁ??」と。
それを聞いて、「ちょっと、ちょっと!」と、突っ込みを入れたくなった。
パーソナリティーはまだしも、「局アナ」はそれではいけませんな。
ベリカードは局が発行しているもの。それを局の職員である「局アナ」が知らないのは、局として「はずかしくない?」
会社がちゃんと社員教育していないか、軽視している証拠。
せめて「うちの局はかっこいいベリカードを発行しているので、ぜひ受信報告書をお送りください」くらいの心の広さが欲しいな。
そもそも、こういう状況になっているのは、ベリカードに対する局の姿勢が如実に反映されているからでしょう。
ほんとうに、局の余裕のなさというか、もうけ主義の少数派切り捨て合理主義者というか、理念や哲学の欠落というか・・
「社会を楽しくしたり、充実したものにするという」人としての心を大切にしてほしいものです。
BCLの魅力
2020.10.1 記
その後、たびたびRAE(日本語)5850kHzを受信してみるが、なかなか聞こえない。
簡単に聞こえないからBCLはおもしろい。
電離層の状態は予想できない「宇宙規模の自然」で、時の運も加わる。
ノイズやフェーディングという荒野の中から遠くの音が聞こえてくる、そこに広大な空間を感じるからだ。
昭和時代のBCL少年たちは、そんな不思議な空間をどこかで感じ、魅力に感じていたに違いない。
もうひとつの魅力は、BCLは「つり」にも似ている。見えない相手にあれやこれや仕掛けを考え、作り、釣り上げる。
受信機、アンテナ、等々、トライ・アンド・エラーをくりかえしている最中がおもしろい。
RAE(日本語)5850kHz
2020.8.5 記
RAE(日本語)5850kHzが聞こえました。
17:00過ぎではUSB側でビートのみでしたが、17:30過ぎには音が取れ上田アナの声が聞こえました。
この時間帯になるとAMでもノイズの中で何かおしゃべりが確認できます。
うちの近くに太陽光発電のノイズなどがあるのか?いつもパタパタノイズかあって悩ませられます。
このパタパタノイズは不思議なことにUSBやLSBで聞くと、どちらかでバッサリ取れることがあります。
ついでにこのバンドに出でいるブラジル局を探ってみると6080kHzでR・Marumby(10kW)がUSB側で聞こえました。
内容は説教のようで、不思議なイントネーションの叫びが聞こえました。
お盆期間は南米もよさそうです。
ついでに。夜になると17MHz帯の局が良く入感しています。サウジなどの中東局も聞こえますよ。
受信機 IC-R75
アンテナ 「短波用アクティブ・ループ・アンテナの製作」 ΔLOOP10
RAE(日本語)5850kHz
2020.5.27 記
久々にRAE(日本語)5850kHzを受信してみた。
時間は17:00-18:00(火曜〜土曜・曜日によって時間変則があるもよう)で、ほぼビートはとれているものの、音声にならない時間が多かった。
時より音になっても、変なノイズというか、連続ノイズ音があり、
上田アナらしきの声がわかるものの、聞きとりは不可能といった感じ。
RAEはアルゼンチンの放送局だが、アメリカのWRMI(100kW)フロリダ付近、の中継局から送信されている。
条件次第では聞き取りも可能になりそう。受信難易度が高いのでBCLマニアにはうれしい局だ。
受信機 IC-R75
アンテナ 「短波用アクティブ・ループ・アンテナの製作」 ΔLOOP10
モンゴルの長波局
2020.5.5 記
ロシアの長波局がなくなって、長波を聞くことがなくなっていました。
しかし、残るモンゴルの局があるので、聞いてみました。
周波数は、164kHz 500kW 209kHz 75kW 227kHz 75kWとのこと。
17時に聞いてみると、それぞれの周波数でSSBでビート音だけ確認できる程度でしたが、21時には209kHzで
弱いながらもAMモードで聞こえました。
大出力の164kHzが聞こえそうなのですが・・・。変更されているのかもしれません。
受信機 IC-R75
アンテナ 「短波用アクティブ・ループ・アンテナの製作」 ΔLOOP10
最近の70'、80'の日本のBCLラジオのオークション状況
2020.4.13 記
最近になってRF-2200に魅力を感じ、久々にオークションサイトを覗いている。
70'、80'の日本のBCLラジオのオークションの落札価格は10年前より上がっているようだ。
さすがにICF-5500のジャンク、おみくじ個体も低価格では落札できないようだ。
アメリカから送られてきたBCLラジオ
2020.4.13 記
「セカイモン・日本」でオークションに参加できるようになった2009年頃の話。
日本では、70'、80'の日本のBCLラジオは今と同じように、ヤフオクで盛んに売り買いされていた。
セカイモンでは当時、日本ではほとんど手に入らない、ICF-5500W、5500Mが手ごろな価格で手に入ったが、アメリカから送られてきた個体を見てびっくりしたことがあった。
どれも電池室のスプリングがピカピカなのだ。定かではないが、これはアメリカが湿度の低い国だからだろうと思った。日本は湿潤な土地で、長年押入れにしまい込んでいるとサビが出るのだろう。
この10年の間にR・Rossiの長波がなくなり(2014年1月)、灯台放送がなくなり(2016年9月)、さみしい
2020.4.13 記
BCLの醍醐味に長波の受信があった。長波ではR・Rossiが279kHzなどに出ていて楽しませてくれたが今やモンゴルしかなくさみしい。
国内では1669kHzの灯台放送が面白く、たった出力50W局が各地から聞こえる、聞く楽しみがあった。
山梨県からの一番の難関は沖縄県宮古島の「みやこじま」で「こちらは・みやこじま・みやこじま・・」とかすかに聞こえる音に耳を傾けた。
70'、80'の日本のBCLラジオ
2020.4.13 記
一時期、オークションで安い70'、80'の日本のBCLラジオを集めた。
動機は「昭和遺産」としての価値を感じているのと、雑誌の記事を書くためだった。
それでも高価なICF-5900や、RF-2200以上のものはやめていた。実践機として使う気がないのと、「どうしても」欲しいものではないからだ。
それでも集めたものは、せっかくだからRP-8700やRP-775Fはこのサイトでもインプレてみた。
他サイトでは70'、80'の日本のBCLラジオのインプレが少ないので、他の手持ちの機種も、インプレしようと思うこともあるが、「俺!こんなにもってるんだぜぇ!」と、ただの御自慢サイトに見られそうなので、増やさない経緯がある。
1620kHz・路側帯放送
2020.4.13 記
BCLでいつも聞くのは、1620kHz・路側帯放送。
夕方から夜になると同じ周波数に各地からの音が重なって聞こえてくる。
SSBまたはLSBモードで、TWIN・BIT (機種IC-R75) を回し調整すると局が浮き出てくる。
ローテーターでアンテナを西に向けると、「名阪国道」が常連で、アンテナの方向次第で北陸方面や関東方面の局も聞こえる。
IC-R75のDSPユニット
2020.4.13 記
IC-R75でDSPユニット(別売り)を付けると、デジタルノイズリダクションが追加される。
レベルは1〜15まであり、レベルを高くするほど音がこもったり、ひずんだりするので通常1〜3程度が使いどころ。
実際に「レベル15まであっても使えねーじゃん!」と思うが、信号が弱い電波にはレベルを上げても音がひずまずに、浮き出てくるようになるのでお試しあれ。
日本製、低価格・BCL通信機型受信機
2020.4.13 記
私が通常使っているのは、アイコムのIC-R75。
BCLを復活した2008年頃に購入した。もちろん通信機型としては一番安で、評判もまあまあだったからだ。
当時でも販売年数が長く、いつ生産中止となってもおかしくない状況だった。さすがに現在は生産中止となったが、それでも愛好者からの要望が多かったらしく、生産中止に至るまで少し伸ばしたようだ。
現在、通信機型で低価格(6万円程度)で手に入るのは、アルインコのDX-R8だけになってしまったが、この機種でも楽しめそう。オークションでバカ高い70'、80'の日本のBCLラジオと比べれば、そりゃもう天地の差まではいかないまでも、実践に最適。